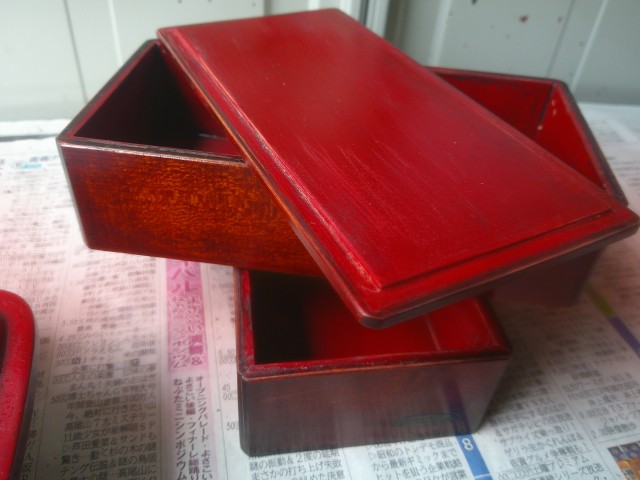2025/06/19(木)
05:00
2025/06/16(月)
13:36
2025/06/16(月)
05:20
2025/06/10(火)
13:42
2025/06/08(日)
14:48
2025/06/07(土)
18:09